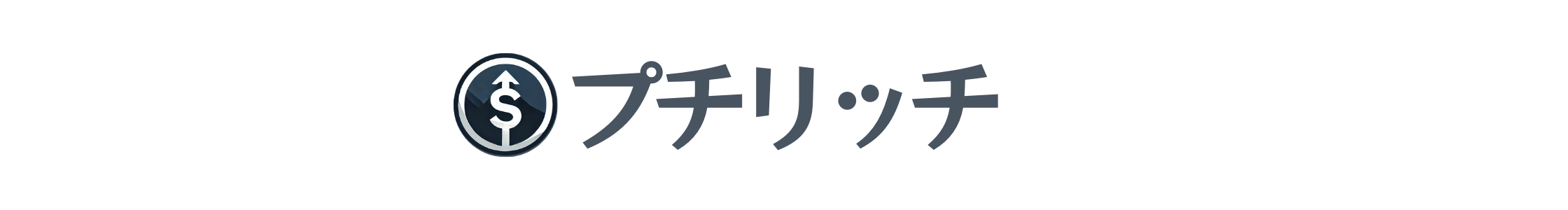こんにちは、ソウリンです。
皆さんは神社参拝をするとき、どんな気持ちで訪れていますか? 私は仕事の合間を縫って全国の神社を訪れるのが趣味なのですが、その中でも特に印象に残っている神社があります。それが今回ご紹介する佐賀県にある「祐徳稲荷神社」です。全国に約3万社ある稲荷神社の中でも、伏見稲荷大社、笠間稲荷神社に次ぐ第三の稲荷として知られる名所です。朱色の社殿と豊かな自然が織りなす景観は、訪れる人の心を癒やすだけでなく、強いパワーを感じられる場所でもあります。今回は私が実際に訪れて感じた祐徳稲荷神社の魅力と参拝方法について詳しくお伝えします。
祐徳稲荷神社の魅力とは?佐賀が誇る絶景スポット
祐徳稲荷神社は、佐賀県鹿島市にある九州最大の稲荷神社です。1687年(貞享4年)に鹿島藩主・鍋島直朝公が京都の伏見稲荷大社から分霊を勧請して創建されました。私が初めて訪れたとき、その壮大さに圧倒されたことを今でも鮮明に覚えています。
朱色の社殿と壮大な景観
祐徳稲荷神社の最大の魅力は、何と言ってもその壮観な朱色の社殿です。特に楼門と本殿は国の重要文化財に指定されており、その美しさは息を呑むほど。山の斜面に建てられた社殿から眺める有明海の景色は、まさに絶景と言えるでしょう。
写真スポットとしても人気なので、カメラを持参することをおすすめします。
商売繁盛・家内安全のご利益
祐徳稲荷神社は、商売繁盛・家内安全・五穀豊穣のご利益があるとされています。特に「お金の神様」としても有名で、経営者や商売をしている方に人気があります。私自身、重要な仕事の前には必ず参拝するようにしています。
四季折々の美しさ
祐徳稲荷神社の魅力は、四季によっても変わります。春には桜、夏には新緑、秋には紅葉、冬には雪景色と、訪れる季節によって異なる表情を見せてくれます。個人的には、紅葉の時期がとりわけ美しいと感じました。朱色の社殿と紅葉のコントラストは、まさに絶景です。
祐徳稲荷神社の正しい参拝方法
神社参拝には作法があります。祐徳稲荷神社でも基本的な参拝方法は同じですが、いくつか特徴的な点もあるので、ここで詳しくご紹介します。
基本の参拝手順
- 鳥居をくぐる前に一礼:鳥居は神域と俗世を分ける境界線です。くぐる前に軽く頭を下げましょう。
- 手水舎での清め:参道に入ったら、まず手水舎で手と口を清めます。右手→左手→口→左手の順番で行いましょう。
- 二拝二拍手一拝:本殿での参拝は、二礼(深く2回お辞儀)→二拍手→一礼(1回深くお辞儀)の順で行います。
祐徳稲荷神社ならではの参拝ポイント
祐徳稲荷神社では、本殿だけでなく摂社・末社も参拝することをおすすめします。時間に余裕があれば、ぜひ回ってみてください。
また、祐徳稲荷神社は山の斜面に建てられているため、多くの階段があります。体力に自信がない方は、ゆっくりと休みながら参拝することをおすすめします。私も最初は息が上がりましたが、その分頂上からの景色は格別でした。
知る人ぞ知る!トイレのお札の秘密
祐徳稲荷神社には、あまり知られていない面白い習慣があります。それが「トイレのお札」です。これは、祐徳稲荷神社で授与されるお札を家のトイレに貼ると、金運がアップするという言い伝えです。
なぜトイレにお札を貼るのか?
実はこれには理由があります。トイレは「うんこ(運呼)」をする場所であり、「お金(御銭)」を流す場所でもあります。そこにお札を貼ることで、「運を呼び、お金が流れ込む」という意味があるのです。
私自身もこの話を聞いて半信半疑でしたが、実際に自宅のトイレにお札を貼ってから、不思議と臨時収入があったりと、良いことが続いた経験があります。もちろん、科学的な根拠はありませんが、心理的な効果もあるのかもしれませんね。
お札の貼り方と注意点
お札は、トイレの扉や壁など、目につく場所に貼るといいでしょう。ただし、あまりにも露骨な場所に貼るのは避けた方が無難です。また、お札は神様の依り代なので、丁寧に扱うことが大切です。
奥の院へのご案内〜ここがおすすめポイント!

祐徳稲荷神社の魅力を最大限に味わうなら、奥の院まで足を延ばすことを強くおすすめします。奥の院は本殿から更に奥に進んだ場所にあり、多くの観光客はここまで来ないため、静かな環境で参拝することができます。
奥の院の魅力
奥の院までの道のりには、約200基の鳥居が連なる「おもかる石」という珍しいスポットがあります。この石は、願い事を思い浮かべながら持ち上げると、叶うなら軽く感じ、叶わないなら重く感じるというもの。私も試してみましたが、確かに不思議な体験ができました。
また、奥の院からの眺めは絶景です。有明海を一望できる景色は、本殿からの眺めとはまた違った魅力があります。特に晴れた日の夕方は、夕日に染まる有明海を眺めることができ、絶好の写真スポットにもなっています。
奥の院参拝のコツ
奥の院まで行くには、かなりの階段を上る必要があります。体力に自信がない方は、途中で休憩を取りながら進むことをおすすめします。また、夏場は特に暑くなるので、水分補給も忘れずに。
私は訪れるたびに奥の院まで足を運びますが、その度に新たな発見があります。特に季節によって異なる景色を楽しめるので、何度訪れても飽きることがありません。
祐徳稲荷神社へのアクセス方法〜佐賀観光の拠点として

祐徳稲荷神社へのアクセス方法は、主に車と公共交通機関の2つがあります。どちらがベストかは、旅行のプランによって異なりますので、ここでは両方の方法をご紹介します。
車でのアクセス
車で行く場合は、長崎自動車道の嬉野ICから約30分の距離にあります。駐車場は無料で、約200台停められるスペースがあるので、週末や祝日でもそれほど心配する必要はありません。ただし、紅葉シーズンなど特に混雑する時期は早めの到着をおすすめします。
私は前回、レンタカーで訪れましたが、カーナビがあれば特に迷うことなく到着できました。周辺は道路も整備されているので、運転に自信がない方でも安心です。
公共交通機関でのアクセス
公共交通機関を利用する場合は、JR長崎本線の肥前鹿島駅からバスや徒歩で向かうことになります。肥前鹿島駅からは祐徳稲荷神社行きのバスが出ていますが、本数が少ないので事前に時刻表を確認しておくことをおすすめします。
また、肥前鹿島駅からタクシーを利用すると約10分で到着します。複数人での旅行なら、タクシーの方が時間や費用の面でも効率的かもしれません。
おすすめの訪問時間帯
祐徳稲荷神社は朝8時から夕方5時まで参拝可能です。個人的におすすめなのは、午前中の早い時間か、夕方近くの時間帯です。特に午前中は参拝客も少なく、静かな環境で参拝することができます。
また、先ほども触れましたが、夕方は夕日に照らされる社殿が特に美しいので、写真撮影を楽しみたい方にはこの時間帯がおすすめです。
祐徳稲荷神社の魅力とは?佐賀が誇る絶景スポット
祐徳稲荷神社は、佐賀県鹿島市にある九州最大の稲荷神社です。1687年(貞享4年)に鹿島藩主・鍋島直朝公が京都の伏見稲荷大社から分霊を勧請して創建されました。私が初めて訪れたとき、その壮大さに圧倒されたことを今でも鮮明に覚えています。
朱色の社殿と壮大な景観

祐徳稲荷神社の最大の魅力は、何と言ってもその壮観な朱色の社殿です。特に楼門と本殿は国の重要文化財に指定されており、その美しさは息を呑むほど。山の斜面に建てられた社殿から眺める有明海の景色は、まさに絶景と言えるでしょう。
私が訪れたのは晴れた日の午後でしたが、夕日に照らされる朱色の社殿は言葉では表現できないほど美しかったです。写真スポットとしても人気なので、カメラを持参することをおすすめします。
四季折々の美しさ
祐徳稲荷神社の魅力は、四季によっても変わります。春には桜、夏には新緑、秋には紅葉、冬には雪景色と、訪れる季節によって異なる表情を見せてくれます。個人的には、紅葉の時期がとりわけ美しいと感じました。朱色の社殿と紅葉のコントラストは、まさに絶景です。
祐徳稲荷神社周辺の魅力的な観光スポット
祐徳稲荷神社の参拝だけでも十分素晴らしい体験ですが、せっかく佐賀まで来たのであれば、周辺の観光スポットも巡ってみてはいかがでしょうか。実は鹿島市周辺には、魅力的な観光地がたくさんあるんです。
鹿島市内の見どころ
酒蔵通り
祐徳稲荷神社から車で約10分の場所には「酒蔵通り」があります。ここは江戸時代から続く酒蔵が軒を連ねる歴史ある通りで、「肥前浜宿」とも呼ばれています。レトロな街並みを散策するだけでも楽しいですが、いくつかの酒蔵では試飲や見学もできるので、日本酒ファンにはたまらないスポットです。
干潟公園(ガタリンピック会場)
有明海に面した「干潟公園」も見逃せないスポットです。ここでは毎年5月に「ガタリンピック」という泥まみれになって競技を行うユニークなイベントが開催されています。イベント時期でなくても、広大な干潟の風景は圧巻で、特に夕暮れ時の景色は絶景です。
干潟の生き物観察も楽しめますので、お子さん連れの方にもおすすめです。
少し足を延ばして訪れたい周辺スポット
嬉野温泉
祐徳稲荷神社から車で約30分の場所には、佐賀を代表する温泉地「嬉野温泉」があります。美肌の湯として知られるこの温泉は、一日の疲れを癒すのに最適です。私も祐徳稲荷神社参拝後に立ち寄りましたが、柔らかな泉質に身も心も癒されました。
宿泊するのはもちろん、日帰り入浴施設も多数あるので、ぜひ参拝の後に立ち寄ってみてください。
有田・伊万里の陶磁器めぐり
少し足を延ばせば、日本を代表する陶磁器の産地、有田町や伊万里市にも行くことができます。特に有田焼の歴史を学べる「有田陶磁の森」や、伊万里鍋島藩窯の歴史を伝える「大川内山」は、陶磁器ファン必見のスポットです。
祐徳稲荷神社を訪れる際に役立つ情報
最後に、祐徳稲荷神社を訪れる際に知っておくと便利な情報をいくつかご紹介します。事前に確認しておくと、より充実した参拝になるでしょう。
おすすめのお守りとお札
祐徳稲荷神社では、様々な種類のお守りやお札が授与されています。特に「商売繁盛」「金運上昇」に関するものが人気です。先ほどもお伝えした「トイレのお札」は、他の神社では見かけない珍しいものなので、ぜひチェックしてみてください。
服装と持ち物のアドバイス
祐徳稲荷神社は山の斜面に建てられているため、かなりの階段を上る必要があります。そのため、歩きやすい靴と動きやすい服装で訪れることをおすすめします。特に女性の方はヒールなどではなく、スニーカーのような平らな靴がベストです。
また、夏場は非常に暑くなるので、帽子や日傘、水分補給のためのドリンクを持参することをおすすめします。逆に冬場は風が強いことがあるので、防寒対策もお忘れなく。
まとめ:祐徳稲荷神社で感じる日本の神秘と佐賀の魅力
祐徳稲荷神社は単なる観光スポットではなく、日本の伝統文化と信仰が息づく場所です。朱塗りの社殿と壮大な自然が織りなす風景は、写真では伝えきれない感動があります。多くの人が伏見稲荷や笠間稲荷に目を向ける中、祐徳稲荷神社は「隠れた逸品」とも言える存在でしょう。
特に興味深いのは、トイレにお札を貼る習慣のような、他では見られない独自の文化です。これは形式的な信仰ではなく、日常生活に溶け込んだ生きた信仰の形と言えるでしょう。現代社会では失われつつある、こうした素朴な信仰心に触れる経験は、私たちの心に何かを残してくれるはずです。
佐賀県という地方都市に、こんなにも魅力的なスポットがあることに驚かされます。東京や京都のような大都市の観光地に比べれば知名度は低いかもしれませんが、だからこそ混雑せずにゆったりと参拝できる良さがあります。地方の隠れた名所を訪れることで、新たな日本の魅力に気づくことができるのではないでしょうか。
皆さんもぜひ、佐賀の地で祐徳稲荷神社の神秘的な雰囲気を体感してみてください。きっと心に残る素晴らしい体験になるはずです。